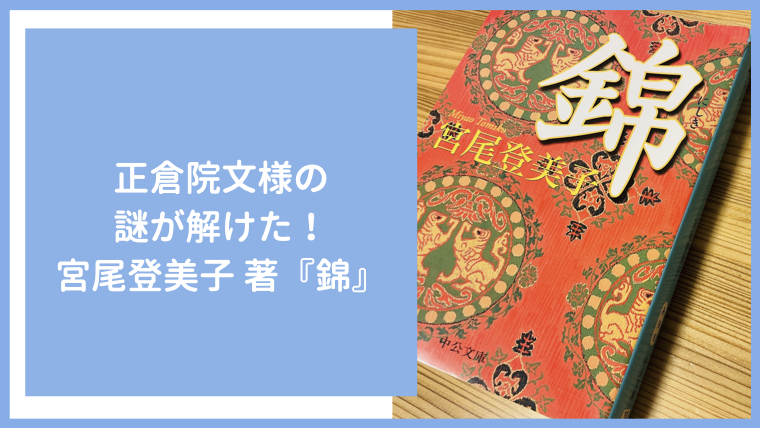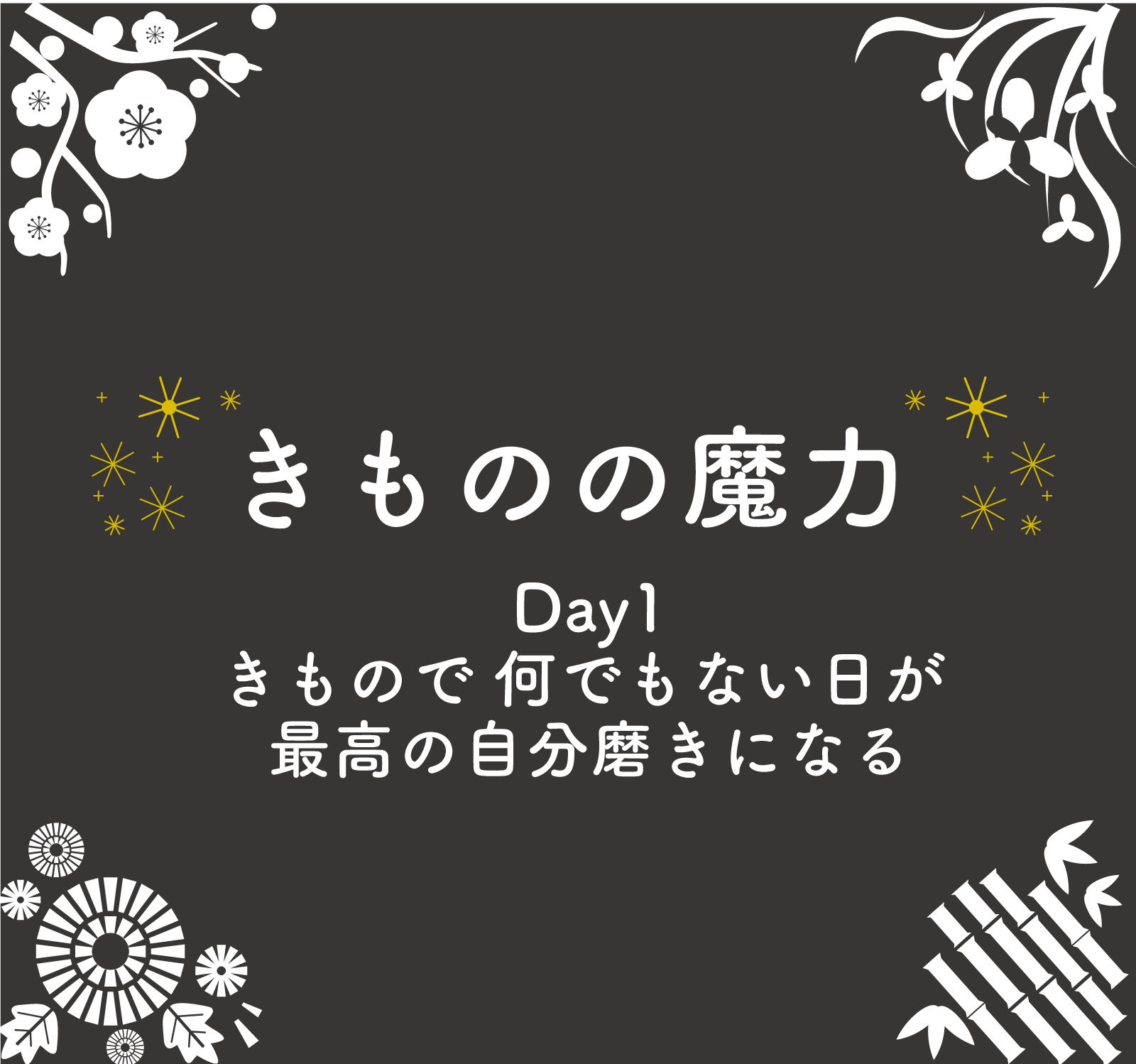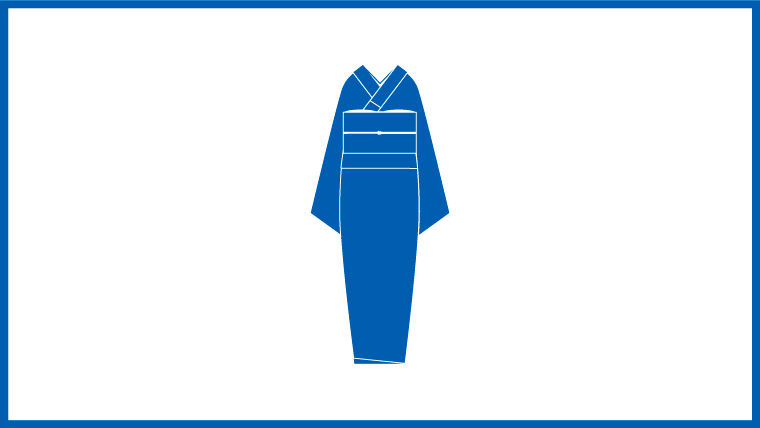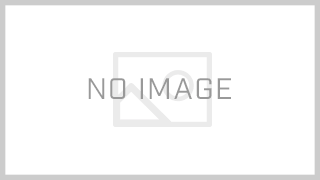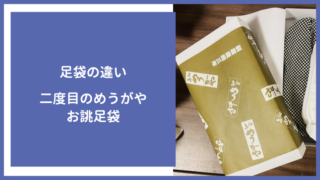こんにちは。上杉惠理子です。
ここ数日、この小説がおもしろくて^^ 久しぶりにどっぷり小説の世界に浸かって読みました。
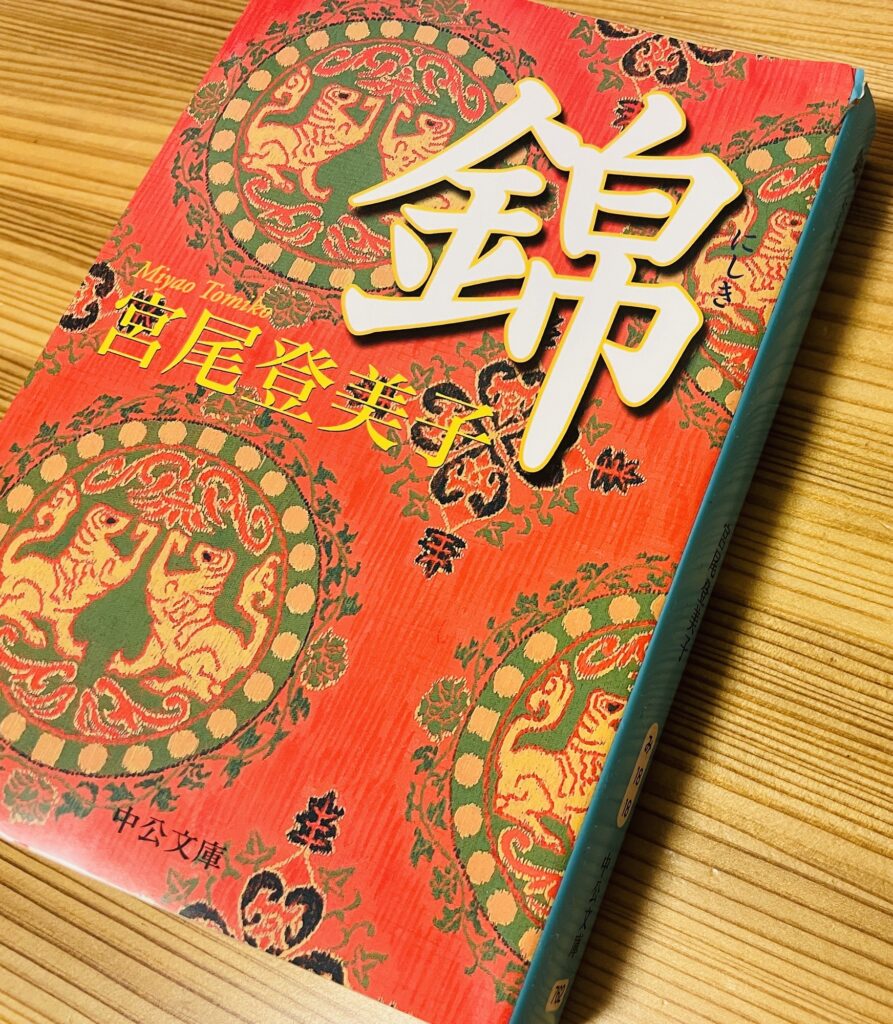
宮尾登美子 『錦』
この小説は、京都 西陣の帯メーカー 龍村(たつむら)の初代 龍村平蔵をモデルにしたもの。
明治9年に大阪で生まれ、18歳で西陣の織元として独立。
当時でもう西陣は織物の街の伝統があったので、よそ者として既存業界とたたかいながら、独自の織物技術を生み出していきます。
もともと着物の帯を作っていましたが、法隆寺や正倉院の高級布 錦の復元も任されるようになり、皇室の依頼でタペストリーなども手がけました。
一代で龍村を、西陣を代表する、いやむしろ日本を代表する織元にした初代 龍村平蔵の物語。
龍村といえば、日本全国の劇場やホールの緞帳も手がけています。現在の歌舞伎座の緞帳も龍村です。
ちょうど昨年、5代目が龍村平蔵を襲名し、着物分野にとどまらないご活躍だそう^^
そんな龍村の初代をモデルにした宮尾登美子の小説『錦』
現代では通用しないパワハラ的シーンもたくさんありますが… ビジネス小説としても読み応えがありますし、彼を支えた女性たちや仕事のパートナーや職人たちとの複雑な人間模様もおもしろい^^
私が一番惹かれたのは
正倉院の錦の復元のシーンでした。
着物の文様に、正倉院文様というジャンルがあります。
正倉院は、奈良時代に大仏を建てた聖武天皇ゆかりの品が眠る蔵。琵琶などの楽器、鏡や箱、肘枕など調度品など、ざっと9000件が現在も残っています。
奈良時代は、遣隋使、遣唐使が中国に送られて大陸の文化を学び吸収していたときでしたので、中国のものや、ササン朝ペルシア(現在のトルコやイラン)からシルクロードを通って来た品やデザインのものが多いのが正倉院。
世界的にも貴重なものが多く、1300年前の木造建築の蔵が現存しているのも世界唯一だそう。
この正倉院の宝物とそのデザインを文様にしたのが、正倉院文様。
大陸の風を感じるデザインで私も好きです^^
文様で世界は繋がっているんだな〜〜と感じます。
そして現在、着物の教科書を開くと、
「正倉院文様は日本最古の文様で最高の格式」つまりフォーマル中のフォーマル、と書いてあるわけです。
ですが、個人的に謎だったんですよ。
誰が、いつから着物の文様にして着始めたんだろう???と。
正倉院は、勅封の倉といって、現在も天皇の許可がなければ開けることもできないのです。
1000年の間、何度か調査には入った記録はあるそうですが、明治になってやっと、毎年2ヶ月ほど定期的に開けて調査やケアするようになったんですよ。
そんな厳重に保管されていた宝物が文様になるってどういうこと?と。
それがこの『錦』で、龍村平蔵の物語を読んでやっとわかった!!
織元として、布の復元のために正倉院に入った初めての人が龍村平蔵だったのですね!正倉院に入ることだけでも特別なことだったそうで、背広を新調して入ったそうです。
そして、蔵の中にはこんもりと小さい山があって、それが琵琶を包んでいた布袋が1000年の時を経て塵になった山。
その塵の山からわずかに残っていた切れ端を探し、色や柄を調査して、復元していったそう!!
…想像を絶する。
著者の宮尾登美子さんも、お着物がお好きだった方。
彼女にとっても、龍村の帯は憧れだったそう。
そして、初代の壮絶な織元人生を聞いたことから、小説への着想を得たものの、着想から30年ほどあたためてから書き上げた作品。
『錦』は宮尾登美子の最後の長編小説でもあり、男性を主人公にした珍しい小説です。
宮尾登美子さん、書き上げてくださってありがとうございます!!
という気持ちです^^
お着物好きな方も、そうでない方も、よかったらぜひお読みになってみてください。
和創塾〜きもので魅せる もうひとりの自分〜主宰
上杉惠理子